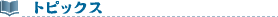
1 第9回MEMS講習会の開催(8月28日)
ファンドリーサービス産業委員会主催(委員長:松下電工(株)富井和志氏)の第9回MEMS講習会「MEMS設計・加工技術と応用例」が、8月28日(火)、アルカディア市ヶ谷(東京・私学会館)で開催しました。
今回は、「MEMSの設計技術」と題して、新たに開発されたMEMSデバイス設計支援用ツール「MemsONE」の概要およびび「MemsONE」を使用したMEMSデバイス設計事例の講演でした。
参加者は81名と盛況で、講習会の中間で技術相談会では、熱心に展示パネルやMemsONEの紹介ビデオを御覧になっていました。
また、講習会の終了後、別室においてファンドリーサービス産業委員会委員、講師の方々と参加者のみなさんとの懇談会を開催しましたが、こちらも大変盛況でした。ご協力有難う御座いました。

MEMS講習会・会場 |

青柳桂一専務理事開会の挨拶 |

立命館大学
杉山 進教授
|

京都大学
小寺秀俊教授
|

技術相談会
MemsONE紹介ビデオ
|

技術相談会
各社技術紹介
|
2 MemsONE β版好調に推移(7月19日~)
新エネルギー・産業技術総合開発機構より委託された「MEMS-ONEプロジェクト成果普及事業」の一環として、MemsONEβ版(プロジェクトの最終成果版)の頒布を6月11日より開始致しました。
β版は実費1万円(ライセンス当たり)で頒布をしておりますが、頒布開始から3ヶ月後の8月末時点において、380ライセンスの申し込みがあり、予想以上の成果を挙げています。事業開始当初の計画では、昨年度に評価用として配布したα版の実績を参考に、“300ライセンス以上”を目標としておりましたが、現時点では新たな目標を“400ライセンス以上”に上方修正致しました。申し込みのピークは過ぎていますが、β版頒布の締め切りは12月末ですから、400ライセンス以上は達成できると期待しています。また、この実績が来年以降にリリースする商用版Ver.1.0(β版および今年度の機能改善・強化版をベースに完成度を向上したバージョン)の販売増加に繋がるものと期待しています。
一方、β版の頒布と共に、MemsONEを日本国内に広く普及させる手段の一つとして、講習会を実施しています。これは、ユーザに使ってもらうには、操作手順や解析方法等のユーザに対する技術的な支援が不可欠だと考えるからです。この支援には、複数のPCにMemsONEβ版をインストールした環境を用意し、実際にPC上でβ版を使ってGUI操作や解析方法を指導する講習会が効果的です。この講習会を実習講座と称し、基本コースと応用コースを用意して7月から来年1月迄の7ヶ月間開催します。本実習講座は、東京大学および京都大学のご協力により実施しており、関東(東京大学本郷キャンパス)で6回、関西(京都大学吉田キャンパス)で3回を開催します。(詳細日程は「イベント開催案内」をご覧下さい。)これまでに、7月19日に第1回京都実習講座(基本コース実習風景7/19参照)、8月22日に第1回東京実習講座(基本コース実習風景8/22参照)、8月27日に関西のプロジェクト参画企業を対象とした実習講座を開催し、計53名の参加者がありました。
京都大学での基本コース実習風景(7/19)
東京大学での基本コース実習風景(8/22)
3 COMS2007報告(8月2日~5日) マイクロ・ナノテクノロジーの商業化、及び人材育成促進に関する国際カンファレンスCOMS2007が9月2日から5日にかけてオーストラリア、メルボルン市で開催され、MEMS協議会の国際交流事業の一環として、松下電工(株)荒川様、みずほ情報総研(株)岩崎様とともに、マイクロマシンセンターも参加しました。
今年で12回目となったCOMSは会場のSOFITEL Hotelを中心に4カ所、計6つ講演会場に分かれ世界から約450名が参加し、16セッションで162件の口頭発表、14件のポスター発表がありました。また同時に開催された展示会には37の企業・機関が出展し、参加企業によるビジネス開発が進められました。
各セッションのトピックスは以下の通りです。
1 基調講演
2 BIO AND LIFE SCIENCES BREADTH AND SCOPE OF NANO BIOTECHNOLOGY SECTOR
3 MANUFACTURING AT SMALL SCALE
4 EMERGING APPLICATIONS
5 EMERGING MATERIALS
6 WATER
7 ENERGY
8 APPLICATIONS AND TRANSFORMATIONS
9 INVESTMENT, LANDSCAPE AND INTELLECTUAL PROPERTY
10 FOOD AND AGRICULTURE
11 GLOBAL OVERVIEW OF SMALL TECHNOLOGIES
12 BUSINESS METHODS- ADVANTAGES AND STRATEGIES USED BY LARGE AND SMALL
PLAYERS
13 PURE PLAY MEMS FOUNDRIES: HOT COMMODITY?
14 SOCIAL AND SOCIETAL IMPACTS NANO ETHI ETHICS AND REGULATIONS
15 HARMST HARMST-LIGA COMMERCIALISATION
16 EDUCATION AND WORKFORCE DEVELOPMENT
日本からは基調講演に産総研の横山様、Bioセッションで名古屋大学馬場先生、Applications and Transformationセッションで東北大学江刺先生が講演され、また、松下電工(株)荒川様はMEMS Foundryセッションで“Wafer Level Packaging Technology at Matsushita Electric Works”の演題で講演されました。
マイクロマシンセンターからManufacturing at Small ScaleセッションでNEDOプロジェクトとして推進しているファインMEMSプロジェクトの紹介”fineMEMS
Project: Technology Development of the Next Generation Micro-Nano Systems“とInvestment,
Landscape and Intellectual Propertyセッションで経済産業省/NEDOが取りまとめたMEMS分野の技術戦略マップ2007の紹介“Towards
Micro-Nano Industry Development: Strategic Technology Roadmap 2007 and
Market Survey in MEMS Area“の2件の講演をし、Global Overviewのセッションで日本におけるマイクロナノシステムの産業化推進について紹介を行いました。
みずほ情報総研(株)の岩崎様は来年度からの推進を要望しているBEANSプロジェクトに関係するナノ・バイオとマイクロシステムの融合について最新の取り組みを調査されました。
参加者のうちオーストラリアからの参加者は全体の2/3を占めていましたが、発表件数でも下図にありますよう45%を占め、オーストラリアがマイクロ・ナノ・バイオへの取り組みに力を入れていることがうかがえます。日本は米国、英国につぎ、ドイツと並び6件の発表を行い会議における日本およびMEMS協議会のプレゼンスを示すことができました。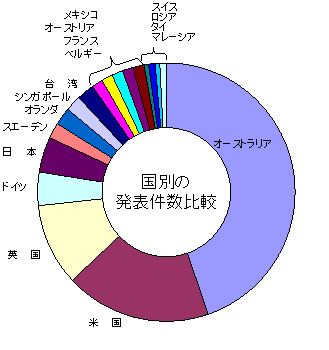
今回のCOMSでは上述のように各国の産業化への取り組みを紹介するセッションがあり、ドイツ、オーストラリア、フランス、英国、米国/カナダ、メキシコ、台湾、シンガポール、日本、タイ、オランダ、スカンジナビアの13の国と地域からの報告がありました。
台湾はITRIを中心に進める技術開発とスタートアップ、ファンドリー育成、シンガポールは世界のR&Dハブとしての戦略的取り組みとベンチャー企業誘致について、タイではナノテク推進という国策の下での繊維・食料産業への重点的な取り組みについて紹介されました。
COMSはMEMS協議会の海外アフィリエートであるMANCEFが開催するイベントでMEMS協議会の活動の一環として日本のプレゼンスを上げていくべきカンファレンスと考えておりますので今後ともご協力お願いします。
尚、来年は8月31~9月4日にメキシコ中部の都市Guadalajaraで開催されます。

COMS会場1
|
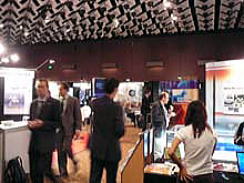
COMS会場2
|
4 シンガポールおよびオーストラリアMEMS研究機関調査報告
COMS2007に参加する機会を利用し、MEMS協議会メンバー企業とシンガポール、及びメルボルンのマイクロ・ナノ関連企業、研究所を訪問いたしました。参加いただいたのは松下電工(株)荒川様、みずほ情報総研(株)岩崎様で、MMCからは安達が同行しました。
訪問先は以下の通りです。
【Singapore】
・National University of Singapore, NanoScience & Nanotechnology Initiative
・A* Star, SIMTech
【Melbourne】
・Small Technology Cluster
・mini FAB
・MONASH University, Centre for Green Chemistry
訪問先概要
◆National University of Singapore, NanoScience & Nanotechnology
Initiative
http://www.nusnni.nus.edu.sg/
大学内の複数の学部、学科が参加し基盤研究領域での現象、プロセス、ツールの発見や開発を目的に組織され、この活動を通じ、ナノサイエンス&テクノロジー領域での長期的な研究競争力の構築、研究人材育成、異分野領域での融合研究の活性化、研究の優先順位と方向性を提供することも狙っている。
国際レベルの研究競争力を確立するため世界に研究機関、企業との連携、人材招聘にも積極的に取り組んでおり、フランス国立科学研究センター、UCサンタバーバラ-MIT-カリフォルニア工科大バイオテクノロジー共同研究体、カリフォルニアナノシステム研究所、ケンブリッジ大学ナノスケールサイエンス研究所、Zyvex社との連携やA*Starや政府機関も参加した研究マネジメント体制を構築し、以下の分野の研究に取り組んでいる。
・Nanobiotechnology
・Nanomagnetics and Spintronics
・Nano/Micro Fabrication
・Nanophotonics
・Nanofiber Science & Engineering
・Health & Environmental Impacts of Nanomaterials
◆A* Star, SIMTech
http://www.simtech.a-star.edu.sg/
SIMTech(Singapore Institute of Manufacturing Technology)はシンガポールの国立研究所で生産技術の研究開発を中心に推進しています。
今回はMulti-functional Substrate Technologyグループを訪問し、グループが推進するLTCC Boutique
Foundry(http://www.ltccfoundry.com/)について情報収集しました。SIMTechのLTCCは多機能高密度な半導体、回路、パッシブ、アンテナの集積の優れたプラットフォームであり、複合材料の製造、高周波特性、及び3次元集積を特長としています。また、特に焼結の際の収縮公差は0.03%と小さい、L/Sが最小35ミクロン、ターンアラウンドタイムが4週間と短いことを強調しています。
この収縮が小さいことが最大40層の積層でスルーホールが確保できるという大きな特長につながっているとのことでした。
企業との連携については1)技術移転、2)パートナーとしてJoint Venture設立、3)小規模の委託研究・ファンドリーの3つの形で進めています。ファンドリーでは2-3パネルの少量から100~250パネルの中規模までを受注している。
また、LTCCの技術を活用したLEDライティング(Solid State Lighting)デバイスの開発も推進しており、低線膨張であることが光源の長寿命化、300度以上の高温耐久性を有し過酷な環境での使用にも適しているとのことです。
◆Small Technology Cluster(STC
http://www.stc-melbourne.com/index.htm
STCはオーストラリア、ヴィクトリア州がマイクロ・ナノ・バイオ関連の産業化を促進するため設立した組織で、現在メンバー企業は12社である。活動内容は、セミナーの開催や政府からの委託研究開発の応募のサポート、メンバー企業の一つであるminiFAB社の保有するクリーンルームの他のメンバー企業との共同使用、オフィススペースのレンタルなどである。
訪問では双方の活動紹介、日本企業のヴィクトリア州への投資について意見交換した。
日本側からは、以下の内容を述べた。
・オーストラリア自体が大きな市場とは思えないので、投資を進めるにはベネフィットの提供が必要。
具体的には優遇税制の設定、優秀な人材確保のサポートなどがある。
・英語圏であるという利点を生かし、海外から優秀な人材を集めることも魅力を高める上で必要。
先方からの要望としては日本企業への効果的なコンタクトの方法について問い合わせがあり、展示 会などへの出展よりむしろ、企業の関連部署にコンタクトすることの方が良いとのアドバイスを行った。
上記項目と関連し、STCからはMEMS協議会に海外アフィリエートとして加入したい旨の要望があり、今後協議を進めることとなった。
◆MONASH大学 Centre for Green Chemistry
http://www.chem.monash.edu.au/green-chem/
グリーンケミストリーとは「環境に優しい化学」の総称であるがより具体的には「環境にやさしい化学合成」、「汚染防止につながる新しい合成法」、「環境にやさしい分子・反応の設計」である。
MONACH大学は日本での知名度は高くありませんが、メルボルン大学とともにオーストラリアを代表する大学で、ある調査では世界の大学院ランキングでも33位にランクされます。ちなみに東京大学は12位、京都大学は29位とのことです。Centre
for Green ChemistryはCOEとして2000年に開設された世界最初のグリーンケミストリーに特化した研究センターで現在42名の大学院生、43名のポスドク、32名の教授・講師で構成されています。代表的な研究例として以下のテーマがあります。
・環境適合酸化触媒
・メゾポーラスマテリアルによる二酸化炭素の固定
・キャピラリー液クロによるバイオ分子の分離
・環境適合性タンパク質のピューリフィケイション
・人に優しい防腐剤
・モレキュラーインプリントポリマーの化学触媒への応用
現在検討中のBEANSプロジェクトに関連するテーマもあり、今後とも動向を注目していきたいと思います。

訪問先:SIMTech
|

訪問先:STC & miniFAB
|
5 大和田邦樹氏(帝京大学教授)IEC1906賞受賞
帝京大学教授の大和田邦樹氏が、今年度IEC1906賞を受賞することが決定しました。
IEC1906賞は、IEC(国際電気標準会議)が1906年の創立から100年になるのを記念して行っている記念行事の一つで、これまでIECの活動に対して、多大な功績のあった個人を顕彰することを目的に、2004年に創設されました。
大和田教授は、マイクロマシンセンターの国際規格化関係委員会、国際規格のフォローアップ関係委員会、海外対応関係委員会の委員長として、MEMSの国際規格の作成・提案、提案規格のフォローアップ、外国提案規格の対応等に中心となって活躍されています。
また、IECには長年、専門家として参画され、特にMEMSの標準化の分野では、2002年よりMEMS標準化を審議していますワーキンググループ、TC
47/WG 4の主査を勤められ、それまで停滞気味だったグループの活動を活性化しました。
これらの活躍によって、日本提案の「MEMS用語集」、「薄膜引張試験法」、「薄膜引張試験用標準材料」の3つの規格を発行することができ、現在「薄膜疲労試験法」が審議中です。MEMS以外にもSC 47E(個別半導体デバイス)でも永年マイクロ波デバイスの国際標準化に携わり、国際議長を勤められる等の功績が認められ今回の受賞となりました。
尚、授賞式は10月15日虎ノ門パストラルにて行われます。

1 MemsONEβ版講習会の開催案内
MEMS用設計・解析支援システム開発プロジェクトが生み出したソフトウェア「MemsONEβ版」の頒布を6月初旬より開始致しました。MemsONEを日本国内に広く普及させるためには、操作手順や解析の技術的なユーザ支援が不可欠です。このため、複数のPCにMemsONEβ版をインストールした環境を用意し、実際にPC上でMemsONEβ版を使ってGUI操作や解析手順を中心に指導を行います。この講習会を実習講座と称し、基本コースと応用コースの2コースを用意しています。開催期間は7月から来年1月迄で、期間の前半は基本コースを、後半は応用コースを予定しています。
○基本コース: フレームワーク操作と解析ソフトの利用方法を指導
○応用コース: 一通り使いこなせる人を対象に解析ソフトの設計・研究に有用な活用方法を指導
この実習講座は、東京大学および京都大学のご協力により実施しています。開催は、関東(東京大学本郷キャンパス)で6回、関西(京都大学吉田キャンパス)で3回を予定しています。
<実習講座の開催月>
| |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
| 関東(東京大学) |
|
8/22
基本 |
9/14
基本 |
10/19
応用 |
11/16
基本 |
12/12
応用 |
1/18
応用 |
| 関西(京都大学) |
7/19
基本 |
|
9/20
基本 |
|
11/9
応用 |
|
|
この実習講座の他に、β版を使った解析事例発表セミナーや他の機関で開催される講習会内でも積極的に開催していく予定です。なお、実習講座は有料ですが、他のセミナーや講習会は無料です。
ユーザの方々には、MemsONEひろば「http://www.mmc.or.jp/mems-one/」の“講習会案内”から、講習会に関する情報を逐次ご案内致します。多くの方々の参加をお待ち致すと共に、この講習会の実施により、MemsONEユーザが拡大することを期待しています。
2 第29回真空展-VACUUM2007の開催案内(9月12日~14日)
日本真空工業会/日本真空協会主催による、「第29回真空展―VACUUM 2007」が下記のとおり開催されますので、ご案内申し上げます。なお、真空展事務局特集展示として、MEMSの概要がパネル展示(6枚)されます。
記
会 期 2007年9月12日(水)~9月14日(金)
会 場 東京ビッグサイト(東京・有明) 東4ホール
開催時間 午前10時~午後5時
詳細及び来場者事前登録はこちら→
http://www.cnt-inc.co.jp/vacuum/
3 MEMS協議会・交流会の開催(11月8日)
MEMS協議会は、MEMS関連企業の構成メンバーを中心として、マイクロナノ・MEMSに係わる大学研究室、地域拠点、海外機関等と連携しつつ、行政、関係機関への政策提言活動や、産業交流・活性化のための諸々の活動を推進しています。
来る11月8日(木)、平成19年度第2回MEMS協議会推進委員会が、行政、関係機関との意見交換を行う「MEMS懇話会」を兼ねて開催されることになっており、この機会に、推進委員会終了後、MEMS協議会の諸活動の理解を深め、併せてMEMS協議会メンバーの相互交流が出来る場として、『MEMS協議会メンバー交流会』を開催することにいたしました。
MEMS協議会メンバー交流会(立食形式)
・開催日時:平成19年11月8日(木) 17:15~19:00
・場 所:商工会館7階 B・C会議室)
東京都千代田区霞ヶ関3-4-2
Tel:03-3581-1634
・参加予定:MEMS協議会企業メンバー(正メンバー、アソシエートメンバー)
MEMS協議会フェロー
MEMS協議会アドバイザー
経済産業省
NEDO技術開発機構
開催については改めてご案内いたしますが、是非ともご参加いただきたく、よろしくお願いいたします。
4 第13回マイクロ・ナノ先端技術交流会(11月9日)
マイクロマシンセンターでは、マイクロ・ナノ技術に関係している賛助会員企業・MEMS協議会企業メンバーの専門家を対象に、マイクロ・ナノ技術に関する各産業分野における先端技術への認識と理解を深めマイクロ・ナノ技術の普及啓発と産学の技術交流を図ることを目的として、年3回、「先端技術交流会」(勉強会)を実施しています。
毎回、2名の先生を講師にお願いし、それぞれご講演をいただき、その後、講師の先生方と技術交流会参加者との懇談会を行います。
第13回マイクロ・ナノ先端技術交流会は、豊橋技術科学大学の石田誠教授、東京工業大学フロンティア創造共同研究センターの秦誠一准教授を講師にお迎えし、以下の内容で開催いたします。
(1)開催日時:平成19年11月9日(金)
13:00~17:00 マイクロ・ナノ先端技術交流会
17:15~19:00 懇談会
(2)開催場所 : マイクロマシンセンター会議室
(3)内 容
○講演①
講師:東京工業大学 フロンティア創造共同研究センター
共同研究機構物質系分野 秦 誠一 准教授
題目:アモルファス合金による微細構造・MEMSの実現
概要:シリコン以外の新素材として,薄膜金属ガラスを中心とした薄膜アモルファス合金を用いた微細構造やMEMSの実現と、用途に応じた材料の最適化・探索手法について述べる。
○講演②
講師:豊橋技術科学大学 電気・電子工学系
石田 誠 教授
題目:集積回路融合による高機能センサ/ MEMS
概要:21世紀COE「インテリジェントヒューマンセンシ ング」などで行ってきたスマートセンサチップのいくつかを紹介する。既存のセンサとICの単なる融
合ではなく、新たなセンサ、機能、性能の向上が期待できる高機能センサ/MEMSを目的とする。
開催案内及び参加申し込み書は、賛助会員、MEMS協議会メンバーにお送りしますので、皆様のご参加をお願いいたします。
5 第10回MEMS講習会の開催(2008年1月21日)
当センターファンドリーサービス産業委員会では、MEMS産業の裾野を広げ、その発展を促進するためにMEMS講習会を開催してきましたが、次回第10回は2008年1月21日(月)東北地方で始めて、宮城県仙台市で開催いたします。
講習会の内容が決まり次第ご連絡しますが、積極的なご参加をお願い致します。
6 2007国際ロボット展について(11月28日~12月1日)
社団法人日本ロボット工業会/日刊工業新聞社主催による、2007国際ロボット展は下記により開催予定ですので、ご案内申し上げます。なお、2007国際ロボット展に特別企画として「マイクロファクトリー実証ゾーン」が設けられます。主催者によると、「本特別ゾーンでは、未来のマイクロファクトリーの実現に向けた様々な機器、製品、ソリューションビジネスを一同に展示・展開される」とのことであります。
財団法人マイクロマシンセンターも本ゾーンにNEDO委託開発事業で開発しましたソフトウェア「MEMS用設計・開発支援システム(MemsONE)」を出展いたします。開発成果でありますMemsONEβ版は、現在多くの関係企業・大学・研究機関等より引き合いがあり、ライセンスを供与する一方、講習会の開催を行っています。この機会に、ぜひMemsONEβ版をご高覧下さい。
記
会 期 平成19年11月28日(水)~12月1日(土)
会 場 東京ビッグサイト 東ホール
開催時間 午前10時~午後5時(最終日は、午後4時30分まで)
予想来場者 10万人
入場料 一般1,000円 学生・団体(15名以上)500円
但し、事前登録者及び招待券持参者は無料
その他 現在、特別企画「マイクロファクトリー実証ゾーン」への出展者を募集中ですので、関
心のある方は2007国際ロボット展事務局(URL: http://www.nikkan.co.jp./eve/ )ま
でお問い合わせ下さい
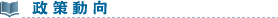
1.経済政策動向
■月例経済報告(8月7日)
8月の月例報告では、景気の基調判断について「景気は、生産の一部に弱さがみられるものの、回復している。」との判断。先行きについては、企業部門の好調さが持続し、これが家計部門へ波及し国内民間需要に支えられた景気回復が続くと見込まれる。一方、原油価格の動向が内外経済に与える影響等には留意する必要がある。としている。
○月例経済報告関係資料
http://www5.cao.go.jp/keizai3/2007/0807getsurei/main.html
■経済産業省の主な経済指標(8月21日)
経済産業省は各種経済指標を取りまとめた資料を発表。たとえば、鉱工業指数(IIP)に関しては、「6月(速報値)の生産は前月比1.3%と4ヶ月ぶりの上昇、出荷は同1.1%と3ヶ月連続の上昇、在庫は同▲0.3%と2ヶ月連続の低下、在庫率は同2.7%の上昇」と分析している。
[概要(PDF)]http://www.meti.go.jp/statistics/downloadfiles/omonakeikishihyo.pdf
[ダイジェスト]http://www.meti.go.jp/statistics/data/hshihyo01j.html
■平成20年度経済産業政策の重点
経済産業省は、8月24日に平成20年度 経済産業政策の重点(平成20年度経済産業省概算要求の概要)を公表した。その中で平成20年度概算要求については、わが国経済の持続的な成長を図る上で、緊急に取り組むべき、「地域・中小企業の底上げ」、「安全・安心の確保と高信頼性産業群の創出」、「地球環境対策」に重点をおいて一般会計全体として1兆1,938億円を要求。又、エネルギー対策特別会計については、8,241億円を要求。としている。
http://www.meti.go.jp/topic/data/070824-1.pdf
■平成20年度産業技術関連予算の概算要求概要
経済産業省産業技術環境局は、上記経済産業政策の重点課題に対応した技術関連予算の要求概要を公表した。その中で、イノベーション創出メカニズムの改革につながるプロジェクトとして、「異分野融合型次世代デバイス製造技術開発」16億円(一般会計)が新規に要求される。この技術開発は、イノベーション25を実現するための革新的未来デバイスとして期待されている。
http://www.meti.go.jp/topic/data/070824-8.pdf
■イノベーション創出を取り巻く関連政策動向
1.温室効果ガスに関する中間報告
環境省の中央環境審議会地球環境部会と経済産業省の産業構造審議会環境部会地球環境小委員会の合同部会が8月10日に開催され、京都議定書目標達成計画の評価・見直しについて中間報告案につい審議した。
京都議定書では、日本の温室効果ガスの排出量を08年~12年度の5年間の平均で90年比6%削減しなければならないことになっている。05年度の実績が基準年度比で7.8%上回っているので公約達成は困難な状況にある。
05年度実績値の部門ごとの排出量の基準年(90年度)からの削減量をみると、排出量のシェアが38%である産業部門が5%強削減されているのに対し、シェアが10%の家庭部門が37%の増、シェアが17%の運輸部門が16%の増、シェアが13%の業務その他部門が45%増と大幅に増えている。
報告書では2010年度の温室効果ガスの排出量は基準年である1990年度比で0.9~2.1%上回ることが予想されるとしている。このため、この排出量を0.6%減となることを目指し国内の省エネ対策を徹底することが求められるとしている。90年比6%減の達成のためには、国内の省エネ対策のほかに森林がCO2を吸収することによる削減分と他国から排出量を購入することで残りの5.4%削減を目指している。
この中間報告を受けて、12月には最終報告書の取りまとめに向け、削減対策について具体化を図ることとしている。
(参考) http://www.env.go.jp/council/06earth/y060-62.html
2.家電リサイクル法の基づく料金前払い方式の導入是非
中央環境審議会家電リサイクル制度評価小委員会と産業構造審議会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルWGの合同会合が7月17日行われ、家電リサイクル法の見直しに関する議論が行われた。家電リサイクル法は平成13年に施行され、施行後5年を経過後に法律の施行の状況について検討を加え必要な措置を講じるとしているが、この合同部会では見直しの一環として現状と問題点について整理を行っている。今回の会合では、これまでの議論の中間的整理を行った。
特に、関心が高いのはリサイクル料金及びリサイクルコストの回収方法であった。リサイクルコストの回収方法について、現行は消費者が家電の廃棄時に支払う方式をとっているが、これを前払い方式にすべきかが問題となった。これに関して、会議では前払い方式は時期尚早であるとの意見が大半を占めた模様である。その理由としては、廃棄家電の相当数が正式な再処理経路に乗っていないので払い損になるのではないかとの懸念からである。
この中間的整理も踏まえ、家電リサイクル法について次期通常国会に改正案を提出することになる。
(参考)http://www.env.go.jp/council/03haiki/y0311-10.html
3. ブルドッグソースの買収防衛策は合法との最高裁の判断
米系投資ファンドのスティール・パートナーズ・ジャパンのブルドッグソース買収防衛策の差し止めを求めた仮処分申請で、8月10日最高裁はブルドッグソースの防衛策を適法とする判断を示した。
ブルドッグソースの対抗策は、スティール社を除く全株主に1株当たり3株の新株予約権を与えるとのものだった。これが成功するとスティール社の株式の割合は当初の3分の1になり、発言権が大幅に減少することになる。スティール社は、この措置は株主平等の原則に反し、著しく不公正であるとして裁判所に訴えたものである。 最高裁は、ブルドッグ社の措置は企業価値の棄損を防ぐもので止むおえなく、また、スティール社は新株予約権を取得できない代わりにブルドッグ社から対価を取得することができるので、株主平等の原則にも反せず著しく不平等でもないとした。
この決定に対しては、海外からの投資が鈍りかねず、また、経営に関する監視機能の観点からは問題であるとの指摘があり、今後ともこのようなケースで裁判所が同様な判断を下すのかどうか注目される。
(参考)http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070807163246.pdf
4.エネルギー革新技術に関する有識者会議初会合
経済産業省は、8月31日に第1回の「クールアースエネルギー革新技術計画」有識者会議を開催した。この会合は、2050年にCO2を半減する総理のイニシャティブを受けて開催されたものであるが、そのために必要な革新的な技術開発を促進することを目的としている。
経産省は、今後10年間を第1フェーズとして革新的なエネルギー技術開発を推進することとしており、年度内を目途に革新技術の開発、国際連携等について提言をまとめ洞爺湖サミットに向けてつなげていくことにしている。
(参考)http://www.meti.go.jp/speeches/data_ed/ed070831j.html
2.産業技術政策動向
■総合科学技術会議開催(6月14日)
第68回総合科学技術会議が6月14日に開催され、議事は以下のとおり。
(1)平成20年度科学技術に関する予算等の資源配分の方針(案)について
(2)競争的資金の拡充と制度改革の推進について
(3)最近の科学技術の動向
(4)その他
なお、配布された資料については、総合科学技術会議(第68回)議事次第参照
http://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/haihu68/haihu-si68.html
また、科学技術の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための第3期科学技術基本計画は平成18年3月28日に閣議決 定されている
[本文(PDF形式)] http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/honbun.pdf
[概要(PDF形式)] http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/gaiyo.pdf
[分野別推進戦略] http://www8.cao.go.jp/cstp/kihon3/bunyabetu.html
■経済産業省の産業技術政策
○産業技術政策の概要(パンフレット)
―技術革新による強靭な経済発展基盤の構築に向けて―
http://www.meti.go.jp/policy/innovation_policy/main_01.files/pamphlet.pdf
○ 経済産業省の研究開発 「技術戦略マップ2007」
http://www.meti.go.jp/policy/kenkyu_kaihatu/
「技術戦略マップ2007」が平成19年4月に経済産業省から発表になっています。技術戦略マップは、新産業を創造していくために必要な技術目標や製品・サービスの需要を創造するための方策を示したもの。
■NEDO産業技術政策関連
○ NEDO海外レポート1003号 「ライフサイエンス特集」 2007.7.4
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1005/index.html
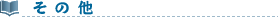
1 経済産業省の人事異動
平成19年8月31日付
(氏 名) (新) (旧)
織田 誠 退職 産業交流部・次長
以上 |